なんでも規制緩和
赤羽一嘉国土交通相は11日の記者会見で、タクシーが飲食物を宅配できる特例を恒久化すると発表した。
タクシー宅配を恒久化 コロナ禍の需要増で 国交省(2020/9/26リンク切れ)
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて9月末まで認める予定だったが、タクシーの収入確保につながり、巣ごもり需要の高まりにも対応できると判断した。
国交省によると、特例の許可を受けたタクシー事業者は9月4日時点で約1700社、約5万4000台。
10月以降も宅配を続けるには改めて地方運輸局への申請が必要となる。
許可期限は2年で延長もできる。
飲食物をトランクに積んで運ぶことなどが条件だ。
要するに「タクシーで宅配」なわけである。

内容の是非についてではなく、これも「規制緩和」なのだ。
きっと、こういったことを規制していたことには意味があったのだろう。
でも、どうしてそうなったかについて、明確にしていかなければ、時代の変化には着いていけないと思うのだよ。
こうした「貨物」と「客」を一緒に運ぶことを「貨客混載」というらしい。

貨客混載という言葉がある位だから、別に難しい話ではないと思う。
wikiには、
日本では、効率の良い大規模輸送や高頻度輸送を目的として客貨分離(例:混合列車、荷物列車、郵便車の廃止等)が進められてきた経緯がある。しかしながら21世紀に入ると、二酸化炭素排出量削減などの環境問題や地方で進行し始めた人口減少対策、さらにトラックドライバー不足などにより、客貨分離が必ずしも効率的ではない状況も見られるようになった。
貨客混載
とある位だから、効率面で現在の形が出来ているような気もするが、貨客混載についての問題点は、いまいち一般時にはよくわからない。

一般人が好き勝手やったあげく、困ったから「助けてドラえもん」って国に泣きつくはめになる予防線として、規制をかけているのは、分からないでもない。
でも規制をかけて、規制で決まっているからなんでもやっちゃだめ・・・・・では、逆に困っている人はどうすればいいんだろうか?
難しい問題ではあるけれど、時代背景によって、規制はどんどん見直していかなければならないと思うのです。
この貨客混載の問題もそれ。
そもそも、貨客混載については、かなり以前からその流れがあることは、以下を見ても分かる。
この記事2017年だからね。
貨客混載が本格化、タクシー会社が宅配便の荷物を配達しはじめた
ドライバーがいても空車増、利用者や収入の減少に悩むタクシー業界と、取扱個数が急増して配達ドライバーの不足に悩む宅配便業界。その両者が手を結べば補完しあえると、国土交通省は2017年9月、タクシー車両で宅配便の配達ができる「貨客混載」の規制緩和を行った。11月には北海道旭川市で、全国初のタクシーによる貨客混載サービスが始まった。しかし条件が過疎地限定のため申請はまだわずか。宅配ドライバー不足が…
なので、今更、この程度の緩和でニュースになるとか・・・・
なんだかなあ。
なのである。
国はもっとドラスチックに規制緩和を・・・・・しないだろうなぁ。
そう思わせる状態だから、気持ちが上向きにならないのだ・・・と思うのだけど。
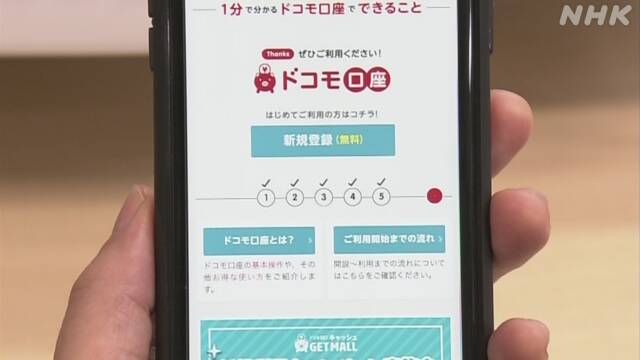
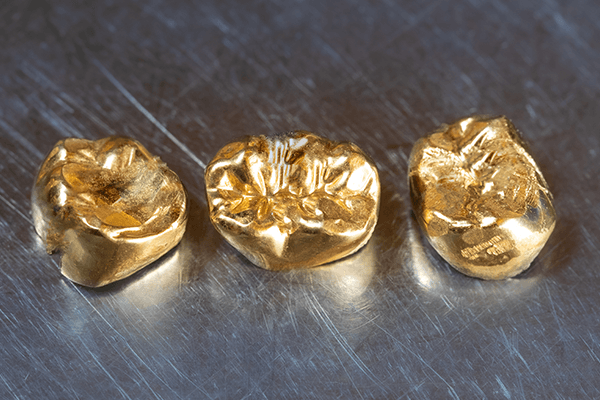


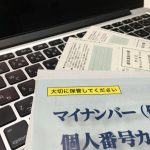

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません