ふるさと納税(1)金額的メリットと落とし穴
ふるさと納税(ふるさとのうぜい)とは、日本の個人住民税の制度の一つで、日本国内の任意の地方自治体(都道府県、市町村および特別区。以下同じ)に寄付することにより、寄付した額のほぼ全額が税額控除されるものである(ただし一定の制限や限度がある)。「ふるさと寄附金」とも呼ばれる。
ふるさと納税、ちょっとしたブームですね。(ちょっとした・・・・ではないかもしれないけど。)

こんなサイトがあったりして・・・・
情報源: ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 全国のふるさと納税を地域・特典・使い道から選べる
で、一体全体何がお徳なんでしょうか?
薄々分かっているのは、
(ふるさと納税をしない場合の所得税+住民税)
より
(ふるさと納税をした場合の所得税+住民税)+(ふるさと納税した金額)-(お礼の品)
の方が金額が低くなるということなんだろうと思っています。
そりゃそうですよね。
いくら、地方創生、地方を活性化しようったって、ブームになるほどみんなが利用しようと思うのは、当然メリットが大きいからに決まっています。
その点は企業版ふるさと納税制度とは大きく違っているようです。
さて、具体的にはどのような計算になるのでしょうか。
多少細かいことは省きますが、おおむね以下のような感じです。

つまり、ふるさと納税した金額から2000円を引いた残りは、所得税と住民税から控除されるということになります。
情報源:ふるさと納税の仕組み
ここでの落とし穴は、所得税並びに住民税からの控除には上限があるということです。
特例控除額の上限が個人住民税所得割額の約1割から約2割に拡充
控除の上限については、こちらでもシュミレーションしてみてください。
情報源: シミュレーション~概要~ | ふるさと納税サイト「さとふる」
40,000円ふるさと納税をすると、自己負担2,000円の負担だと、所得税・住民税合計で38,000円控除できるということになるでしょうか。(控除の上限を超えていなければ。)
例えば年収300万円の夫、妻は専業主婦、子供は高校生三年生1人とシュミレーションにいれると、ふるさと納税の寄付の上限は29,000円(自己負担2,000円、控除27,000円)と出ます。
そして2,000円自己負担については、ふるさと納税のお礼の品というやつで、2,000円以上のお礼(商品)が手に入れば、儲かるということになりますよね。
なるほど、こりゃ、みんなやりますよね。
例えば、20,000円ふるさと納税をすると、鹿児島県鹿屋市の一例では、「真空さつまあげお得な増量セット」をもらえます。
- 真空特上棒天(6本入×5)
- 真空じゃこ天(6枚入×4)
- 真空ごぼう天(6枚入×4)
- 真空いわし天(6本入×5)
- 真空からいも天(6枚入×4)

こんだけ入ってます。
つまりどうせもともとふるさと納税をする20,000円の内、控除される予定の18,000円は所得税・住民税で払うものだったのだから実質的に2,000円でこれが手に入ったという計算になります。
こりゃ、お得ですよね。
まあ金額的なメリットについては、これでおおむねご理解頂けたと思いますが、世の中そんなにうまい話はないと思うので、落とし穴について考えてみます。
①詳細を計算しないと、効率的なふるさと納税はできない。
先ほどは、シミュレーション~概要~ | ふるさと納税サイト「さとふる」の簡易シュミレーションを使って、上限額29,000円が出たと書きました。
しかしながら、控除額計算シートをダウンロードして再計算してみたところ、最も効率の良い(つまり自己負担が2000円までとなる)ふるさと納税額は、24,380円となってしまいました。
こんな半端なふるさと納税額はないでしょうから、20,000円寄付を目指すということろでしょうか。
情報源: ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 2015年ふるさと納税 ワンストップ特例制度を徹底解説!税制改正でふるさと納税の何が変わった?
②上限をきちんと確認しておかないと控除されないこともあり得る。
まあ当たり前の話ですが、自分が納めている税金以上に寄付しても、税金から控除されないことは、分かり切ったことですよね。
でも自分の所得税、特に住民税についていくら納税しているか、また確実に控除される金額はいくらなのかについては、きちんと計算しないと税金の計算式は色々ですから、税金から控除されなかったなんていうことは、かなりありそうです。
③申告しないと控除されない場合がある。
これに類似した例としては、手続きミスというのもあるようですが、実際にふるさと納税をした人の7割が、実は申告をしておらず損をしていたというデータも発表になっているようです。
なんだかなあ。
国税庁はそれを狙ったのでしょうか?
平成25年からはふるさと納税ワンストップ制度という確定申告しなくても、控除の摘要が受けられる仕組みが出来ているようですが
それにしても、申請が必要だそうですし、控除されない人は今後も減りはするでしょうけれど、なくならないでしょう。
◎気になる特産品を選ぶ → ◎寄付金を納める → ◎お礼品と受領証明書を受け取る → ◎税務署に確定申告する → ◎税金の還付を受ける
④自分が居住している自治体にふるさと納税を納めても適用されない場合が多い。
さすがにこれにひっかかる人はいないかなあ。
⑤1年に何回も寄付してもお礼の対象とならない場合が多い。
寄付に対するお礼として提供されている自治体からの特典は、多くの場合1年に1回までとなっています。
中には複数回適用される自治体や、何度でも適用される自治体もあるそうですが。
さらに個人の会計期間は1月1日から12月31日までですが、自治体の会計期間は4月1日から翌年の3月31日までになっていますので、その辺も要注意ですね。
落とし穴はこれ位のようですから、まあ、住民税をある程度納めているなら、是非チャレンジすべきでしょうね。

(続く)
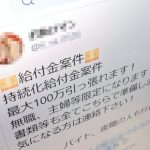

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません