学術会議の「任命拒否問題」
問題(もんだい、英: problem)とは、(問題解決の分野では)現状と目標との間にある障害(差、ギャップ)のことである。
問題

国内の科学者を代表する機関「日本学術会議」が推薦した新会員候補のうち、6人を菅義偉首相が任命しなかった問題
学術会議の「任命拒否問題」に潜む次の問題点
とあるのだが、これの何が問題なのか、いまひとつ分からない。
![ただし、学問の自由は拒否する! - 2016年12月31日のその他のボケ[47177445] - ボケて(bokete)](https://d2dcan0armyq93.cloudfront.net/photo/odai/600/91be0a9533451719fc76bb8c86666502_600.jpg)
曰く、学問の自由が侵害されるという。
学問の自由とは
学問の自由(がくもんのじゆう)は、研究・講義などの学問的活動において外部からの介入や干渉を受けない自由。
学問の自由
と書いてあり、日本学術会議に選ばれることは学問なのか?
そもそも日本学術会議のHPには、
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信の下、行政、産業及び国民生活に科学を反映、浸透させることを目的として、昭和24年(1949年)1月、内閣総理大臣の所轄の下、政府から独立して職務を行う「特別の機関」として設立されました。職務は、以下の2つです。
日本学術会議とは
と書いてあり、「学問」をするのではなく、「科学を反映・浸透させること」が「目的」であり、「総理大臣の所轄の下」で「職務を行う」と書いてあります。
所轄≒管轄≒権限によって支配すること。また、その支配の及ぶ範囲
であり、自ら総理大臣の権限によって支配されると謳っていて、任命されないと、学問の自由があああとか言っていること自体、この人たちの論理的思考を疑う。
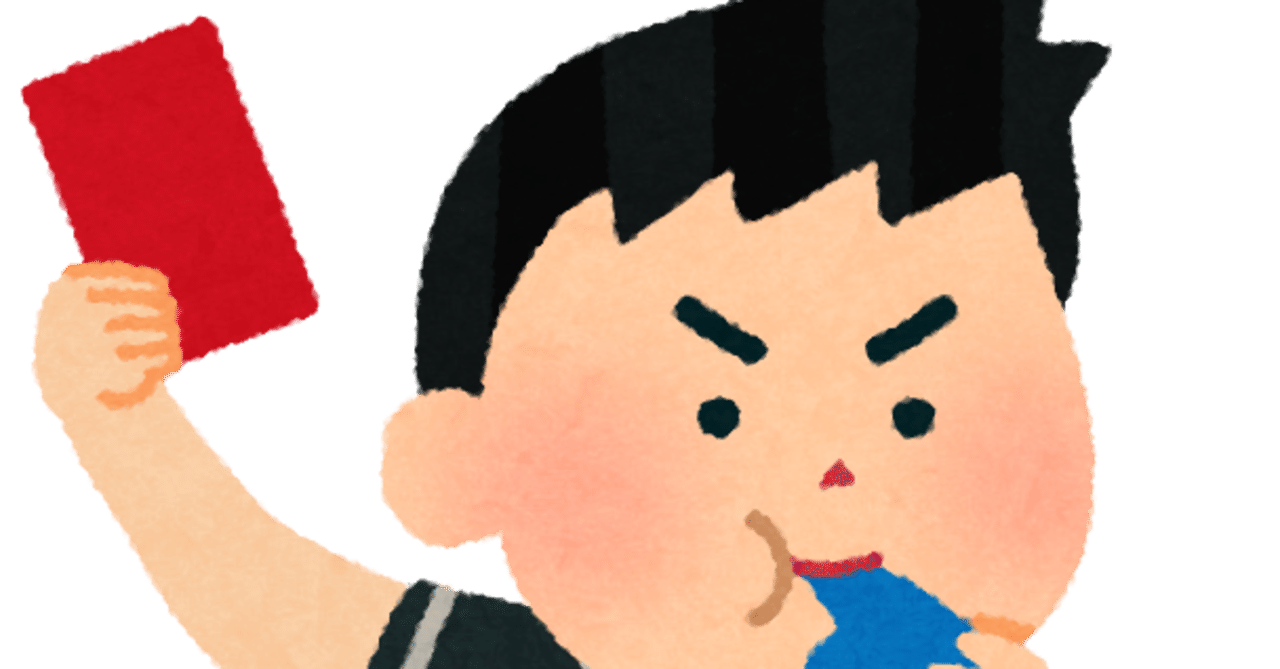
学術会議の「任命拒否問題」に潜む次の問題点では、次に国立大学の学長人事にも波及し、将来任命拒否する可能性があり問題であると言っているが、まずそこに至っていない点、そしてそこに至っても明確な理由があれば問題ない点等々、先を読みすぎで、更にまだ起こっていないことについて論評していることは、論理のすり替えも甚だしい。
これが起こったから、これも起こる可能性があり問題だ!と警鐘をならすのは良いとしても、この国立大学の学長人事さえも、感覚的には意味不明である。
従来の通説的見解によれば、学問の自由の内容には、学問研究の自由、学問研究結果の発表の自由、大学における教授の自由、大学の自治が挙げられる[9]。
学問の自由
学長人事の任命拒否は、大学の自治に影響するかもしれないが、大学の自治が必ずしも損なわれるわけではない。
話を元に戻すと、不思議なのは、
本学術会議法は「優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦」(第17条)し、日本学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」(第7条第2項)こととされている。
学術会議の「任命拒否問題」に潜む次の問題点

任命といいつつ、推薦があれば拒否しないものだという論理展開が、一般人からすればぶっとんでいる。
任命=ある役目につくことの命令。官職に任ずること。
であり、初めての任命拒否と言っているが、命令なのだから、命令する側に権利があるだろうと普通は思う。
そもそも、拒否できないのであれば、それは任命ではなく、まずそういった基本構成から考え直すべきだろう。
それとも何か?
法律用語では任命とは、認めるとか認証するとかいう意味だとでも言うのだろうか?
その点については、政治家よりまず学術会議の人達が、正すべき問題だと思うのだが・・・・・
なんだかなあ。
だからこの話が「問題」な点がいまいち分からない。
任命じゃないなら、総理大臣に任命させないようにしておかないと、まず「問題」なわけで・・・・
何をいまさら・・・・
なんだかなあ。
【追記①】
静岡県の川勝平太知事は7日の定例会見で、「菅義偉という人物の教養のレベルが露見した。『学問立国』である日本に泥を塗った行為。一刻も早く改められたい」と強く反発した。
「教養のレベルが露見」 任命問題、学者知事が強く反発(2020/10/23リンク切れ)
任命権を使って、任命を拒否した人に対して「教養レベル」とかいうのは、ものすごく嫌な感じ。
「おまえ、任命って書いてあるけど、推薦があったら認めるのが普通で、当然なのに、知らなかったんだろう、レベルが低いな。」って言っているみたいで、本当に嫌。
何をどう問題なのかを誰にでも分かるように説明しろよって、本当に思う。
馬鹿には教えてやらないと言わんばかりの言い方にムカつく。
なんだかなあ。
【追記②】
声明では、日本学術会議の高い独立性は法律にも明確に規定されていると説明。
学術会議任命拒否「法律上認められず、違憲」 京都弁護士会が声明(2020/10/21リンク切れ)
会員推薦の基準を満たしているかを適切に判断するのは同会議であり、首相の任命拒否は予定されていないと指摘する。
菅内閣が主張する「総合的、俯瞰(ふかん)的活動を確保する観点」からの任命拒否についても、同会議の自主性・自立性を著しく侵害し、法律上絶対に認められていないと強調。
個々の科学者の学問の自由や表現の自由を侵害し、研究や表現、同会議の選考・推薦行為を萎縮させるとして違憲だと訴えた。
弁護士の集まりのトップなら、もう少し法律的に説明して欲しかった。
日本学術会議が高い独立性を法律にも明確に規定されているとしても、「首相の任命拒否は予定されていない」というのは、どこをどう読めばそうなるのか?
そもそも任命に拒否がないという言い方自体、論理破綻ではないのか?
任命拒否が、自主性・自立性を著しく侵害しているとどこをどう読めばそうなるのか?
それならそもそも任命という条文がおかしいのではないか?
任命拒否が違憲なら、そもそも任命するという条文自体、違憲なのではないのか?
疑問は尽きない。
法律に「予定されていない」とか、意味不明なのだが、これは一般的法律の論理構成なのか?
なんだかなあ。
こう書いてあるけど、本当はこう読むんだよ、それが分からないのは、学問を知らないから、教養が低いからなんていうのは・・・・・一般社会で通用する話なのだろうか?




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません